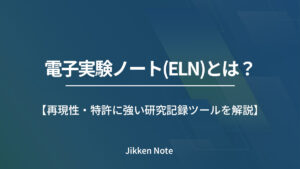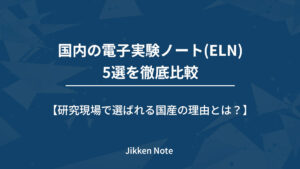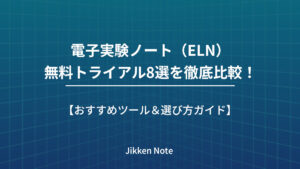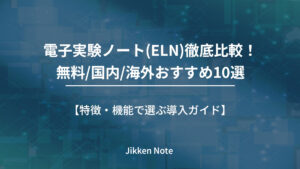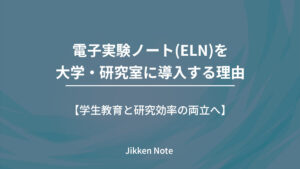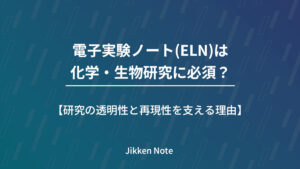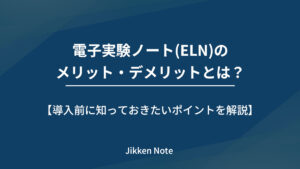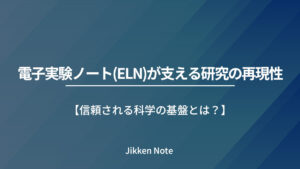海外の電子実験ノート(ELN)8選を徹底比較!特徴・選び方・導入の注意点
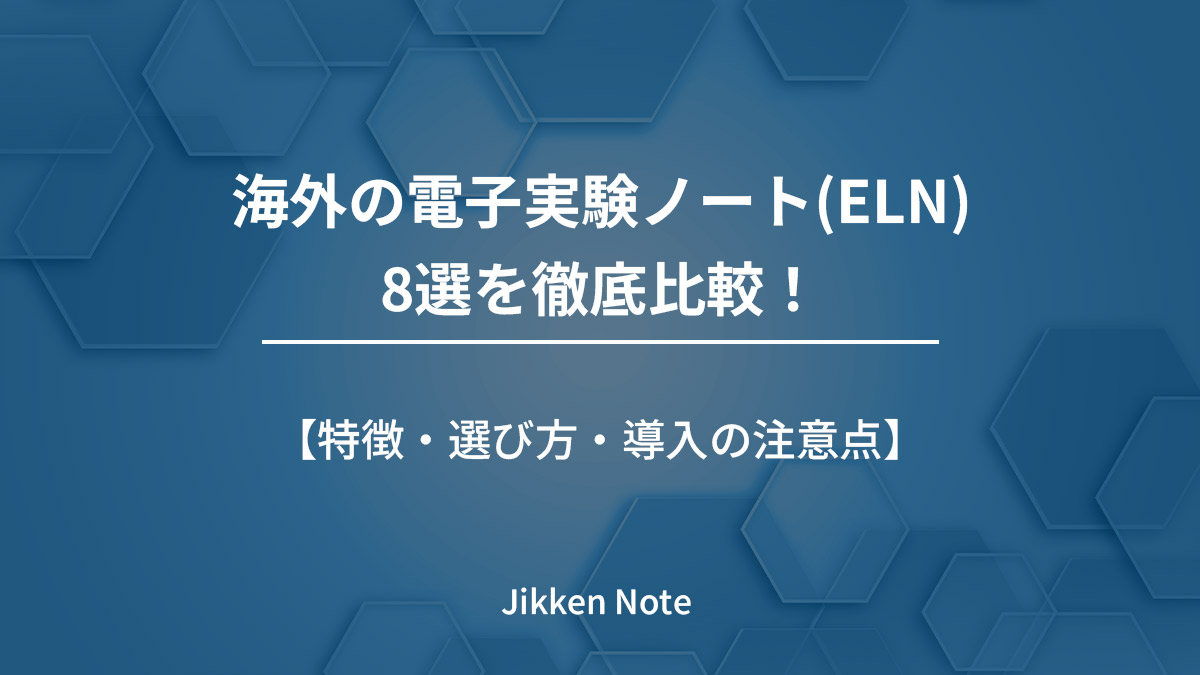
研究データの管理や共有に、紙の実験ノートやExcelを使用していて非効率だと感じていませんか。
特に海外拠点との共同研究が増える中で、グローバルに通用するデータ管理基盤の構築は急務です。
この記事では、海外製の主要な電子実験ノート(ELN)を徹底的に比較し、機能や価格、コンプライアンス対応の違いを明らかにします。
記事を読めば、あなたの研究室やチームに最適なツールを見極めるための、具体的な知識と判断基準が身につくでしょう。
電子実験ノート「Jikken Note」のサービスとは?>>
海外製電子実験ノート(ELN)とは?
電子実験ノート(ELN: Electronic Lab Notebook)は、従来紙媒体で行われていた実験記録やデータ管理をデジタル化するシステムです。
特に海外製のELNは、グローバルな研究環境での利用を想定して開発されており、多くの先進的な機能を備えています。
海外製ELNの定義と代表的な特徴
海外製の電子実験ノートは、単に記録をデジタル化するだけでなく、研究開発プロセス全体の効率化を目指す多機能なツールです。
その多くには、以下のような共通の特徴が見られます。
- 英語ベースのUI:
グローバルな共同研究を円滑にするため、ユーザーインターフェースは基本的に英語で設計されています。 - クラウド(SaaS)での提供:
サーバー管理が不要で、場所を問わずアクセスできるクラウドベースのサービスが主流です。 - 多機能・高機能:
実験記録に加え、データ解析、在庫管理、プロジェクト管理など、研究活動を包括的に支援する機能を備えています。
日本国内でも導入が進む理由
近年、日本国内の企業や大学でも海外製ELNの導入が加速しています。
その背景には、グローバル化の進展により、海外の研究機関や企業との共同研究が一般化したことがあります。
また、研究データの信頼性や再現性に対する要求が世界的に高まっており、国際基準に対応したデータ管理体制の構築が不可欠となっているためです。
海外製ならではの利点(特許・知財対応、GLP/GMP、FDA 21 CFR Part11)
海外製ELNが持つ大きな利点の一つが、厳格な国際規制への準拠です。
例えば、医薬品開発で求められるGLP/GMPといった品質管理基準や、米国食品医薬品局(FDA)が定める電子記録・電子署名に関する規制「FDA 21 CFR Part 11」に対応した製品が多くあります。
これらの機能は、研究データの信頼性を保証し、特許申請や海外当局による査察の際に、強力な証拠能力を発揮します。
海外製電子実験ノート(ELN)を選ぶメリット・デメリット
海外製ELNの導入は多くのメリットをもたらしますが、一方で注意すべきデメリットも存在します。
導入を成功させるためには、両方の側面を正しく理解し、自社の状況と照らし合わせて検討することが重要です。
| 項目 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 機能性 | 最先端の機能(AI/ML、自動化など)が利用できる | 日本の研究スタイルに合わない機能が含まれる場合がある |
| グローバル対応 | 多言語対応や国際規制準拠で海外拠点との連携がスムーズ | 時差や言語の壁により、サポート対応に時間がかかることがある |
| 拡張性 | 豊富なAPI連携により、既存システムとの統合が容易 | 導入やカスタマイズに高い専門知識が求められることがある |
| コスト | 多様な価格プランから選択できる | 高機能なプランは高額になりがち |
メリット:複数言語・多国籍チームで使える
海外製ELNの最大のメリットは、グローバルな研究開発環境への適応力です。
多言語対応はもちろんのこと、世界中のどこからでも同じデータにアクセスし、リアルタイムで共同作業を進めることができます。
これにより、国境を越えたチーム間でのコミュニケーションが円滑になり、研究開発のスピードと質を大幅に向上させることが可能です。
デメリット:導入ハードルが高い
一方で、海外製ELNの導入にはいくつかのハードルが伴います。
まず、多くの製品が英語UIであるため、言語の壁を感じる研究者も少なくありません。
また、高機能であるがゆえに操作が複雑であったり、導入後のサポートが日本語に完全対応していなかったりするケースもあります。
これらの点を事前に確認し、社内でのトレーニング体制を整えることが導入成功の鍵となります。
電子実験ノート(ELN)徹底比較!無料/国内/海外おすすめ10選|特徴・機能で選ぶ導入ガイド>>
【徹底比較】海外の主要電子実験ノート(ELN)おすすめ8選
ここでは、海外で広く利用され、信頼性の高い電子実験ノート(ELN)を8製品ピックアップして、その特徴を詳しく解説します。
各製品の強みや弱み、価格帯を比較し、自社の研究スタイルに最適なツールを見つけるための参考にしてください。
1. Benchling:バイオ・製薬研究の統合プラットフォーム
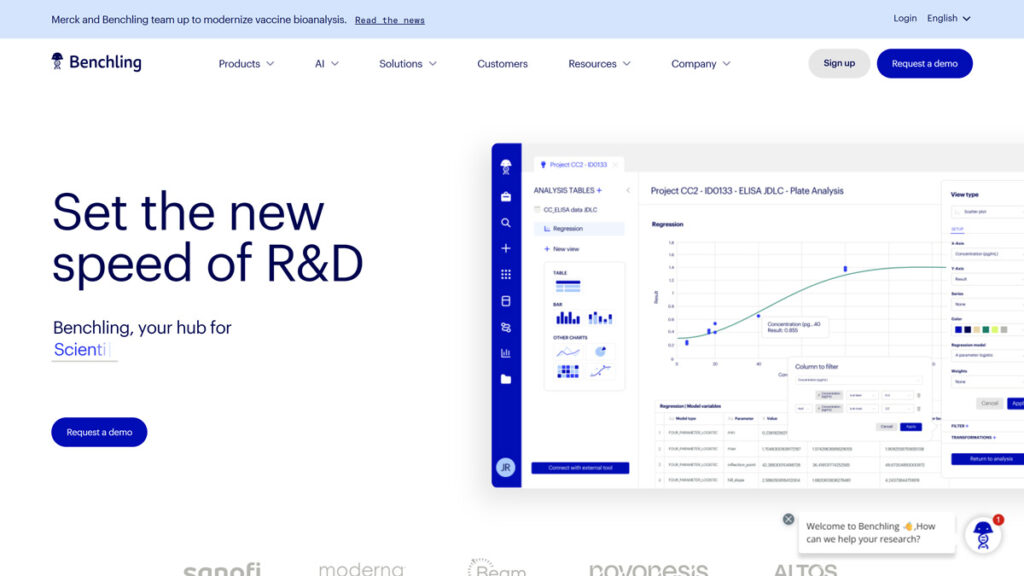
引用元:https://www.benchling.com/
Benchlingは、特にライフサイエンス分野の研究開発に特化した、クラウドベースの統合プラットフォームです。
ELN機能だけでなく、LIMS(実験情報管理システム)や分子生物学ツールまでを一つの環境で提供します。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 主なターゲット | 製薬、バイオテクノロジー、学術研究機関 |
| 強み | ・ELN、LIMS、試薬/サンプル管理を統合 ・モレキュラバイオロジーツールを搭載 ・APIや自動化連携に対応 |
| 弱み | ・エンタープライズ向けは高価格帯 ・導入規模によっては機能過剰になる場合あり |
| 価格帯 | 学術向け:無料プランあり 企業向け:要問い合わせ |
| 導入実績 | 世界の大手製薬・研究機関で採用 |
2. IDBS E-WorkBook:コンプライアンスとデータ信頼性を最重視
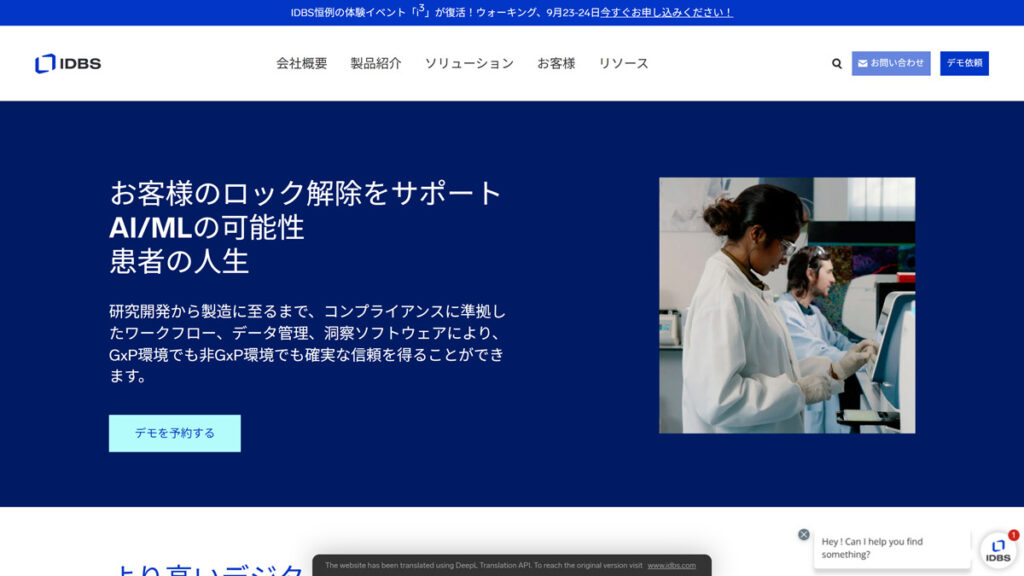
IDBS社のE-WorkBookは、規制の厳しい製薬業界やCRO(医薬品開発業務受託機関)で絶大な信頼を得ているELNです。
データの信頼性(インテグリティ)と規制遵守を最優先に設計されています。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 主なターゲット | 製薬、バイオテクノロジー、CRO |
| 強み | ・FDA 21 CFR Part 11やGxP対応 ・電子署名や監査証跡など強力なコンプライアンス機能 ・研究から製造プロセスまで管理可能 |
| 弱み | ・インターフェースが複雑・導入・運用に専門知識が必要 |
| 価格帯 | 要問い合わせ |
| 導入実績 | 規制対応を重視する製薬企業やCROで広く採用 |
3. LabArchives:アカデミアや小規模ラボ向けの低コストな選択肢
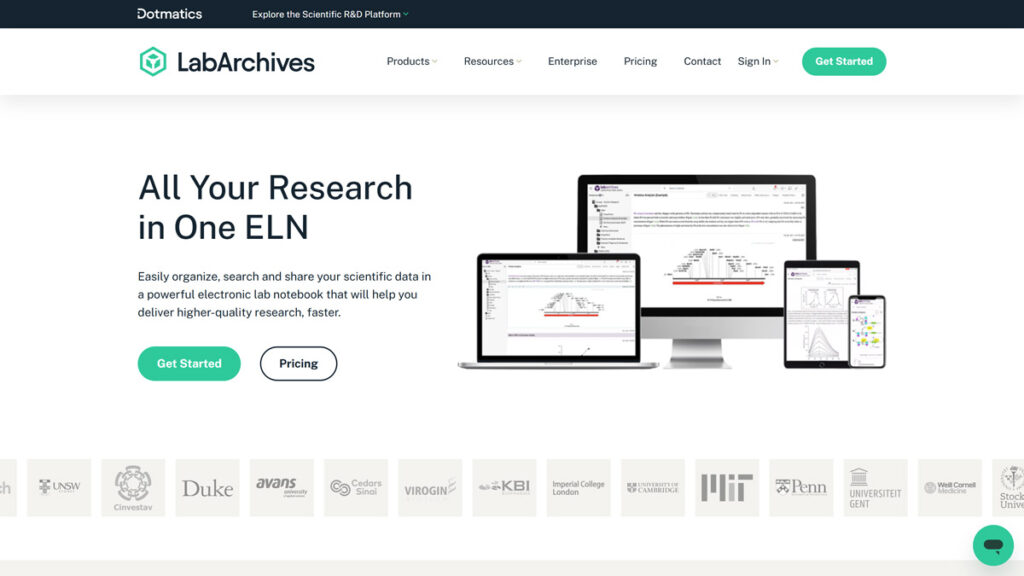
引用元:https://www.labarchives.com/
LabArchivesは、その使いやすさと手頃な価格設定から、大学などの学術研究機関や小規模な企業で広く採用されています。
まずはコストを抑えてELNを試してみたい場合に最適な選択肢の一つです。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 主なターゲット | 学術研究機関、小〜中規模研究室、教育機関 |
| 強み | ・直感的で扱いやすいUI ・Microsoft Officeや科学ツールと連携 ・教育向けプランも用意 |
| 弱み | ・高度な規制対応はEnterprise限定 ・大規模製薬用途には不向き |
| 価格帯 | Freeプランあり Professional:Academic $330/年、Corporate $575/年 Enterprise:要問い合わせ |
| 導入実績 | 多くの大学・教育機関で採用実績あり |
4. SciNote:プロジェクト・在庫管理機能が充実した中小企業向けツール
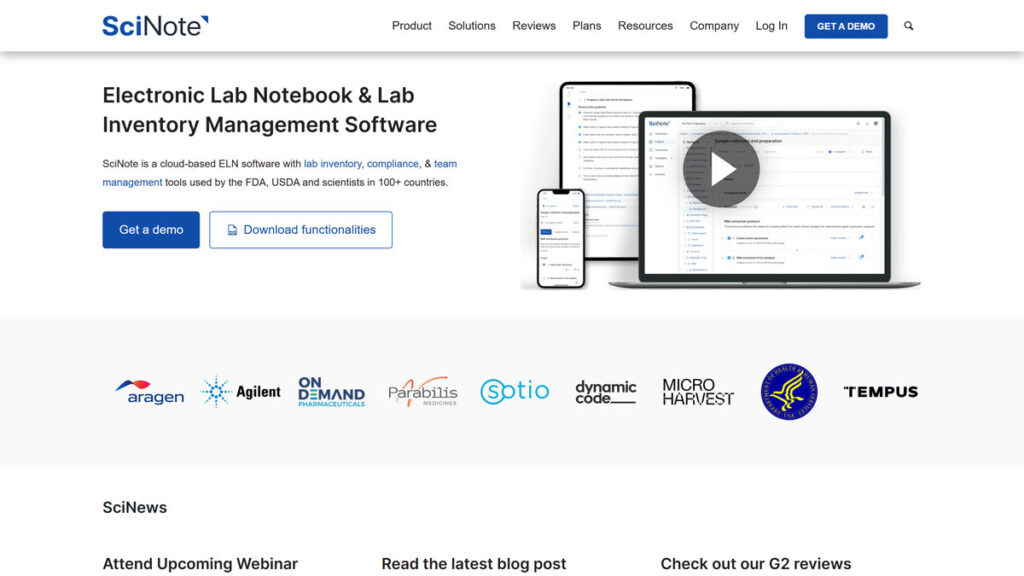
SciNoteは、実験記録だけでなく、プロジェクト管理や在庫管理の機能が統合されている点が大きな特徴です。
研究室全体の運営効率を向上させたいと考えている中小規模のラボに適しています。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 主なターゲット | 学術研究機関、中小規模の企業・研究室 |
| 強み | ・プロジェクト管理や在庫管理が可能 ・監査証跡・電子署名などコンプライアンス機能 ・無料プランあり |
| 弱み | ・無料プランは機能制限あり ・大規模利用には不向き |
| 価格帯 | 無料プランあり 有料は要問い合わせ |
| 導入実績 | 世界100か国以上で利用、政府機関でも採用実績あり |
5. Labguru:実験・在庫・プロトコルを一元管理できる高機能ELN

Labguruは、実験ノート、在庫管理、実験プロトコル、さらには機器管理までを一つのプラットフォームで統合管理できるELNです。
研究室のあらゆる情報をデジタル化し、業務の効率化とデータの関連付けを強力に推進します。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 主なターゲット | バイオテクノロジー企業、学術研究機関 |
| 強み | ・ELN、在庫、プロトコル、機器管理を一元化 ・研究データと実験資源を自動でリンク ・研究トレーサビリティを強化 |
| 弱み | ・多機能ゆえ習熟が必要 ・化学分野特化機能は限定的 |
| 価格帯 | 要問い合わせ |
| 導入実績 | 研究室や企業で幅広く導入実績あり |
6. RSpace:教育機関に特化した柔軟なユーザー管理が魅力
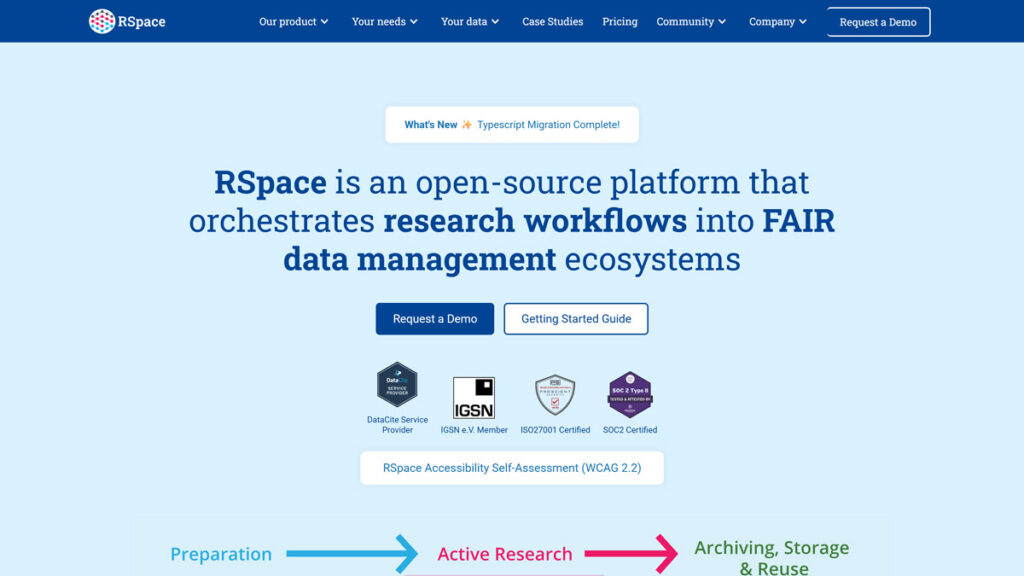
引用元:https://www.researchspace.com/
RSpaceは、特に大学や教育機関での利用を想定して開発されたELNです。
研究室の主宰者(PI)が学生や研究員のアクセス権限を細かく管理できる機能が充実しており、教育・研究の両面で活用されています。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 主なターゲット | 大学、教育機関、研究機関 |
| 強み | ・柔軟なユーザー権限管理 ・オープンAPIで他システムと連携 ・教育機関向け割引あり |
| 弱み | ・商用利用では価格が高めになる場合あり ・産業界での厳格な規制対応は限定的 |
| 価格帯 | Academic:約$4,550/年(15ユーザー)〜 Commercial:約$9,100/年(15ユーザー)〜 Enterprise:$19,500/年〜 |
| 導入実績 | 世界の大学・研究機関で広く採用 |
7. eLabFTW:オープンソースで柔軟性高いセキュアなELN
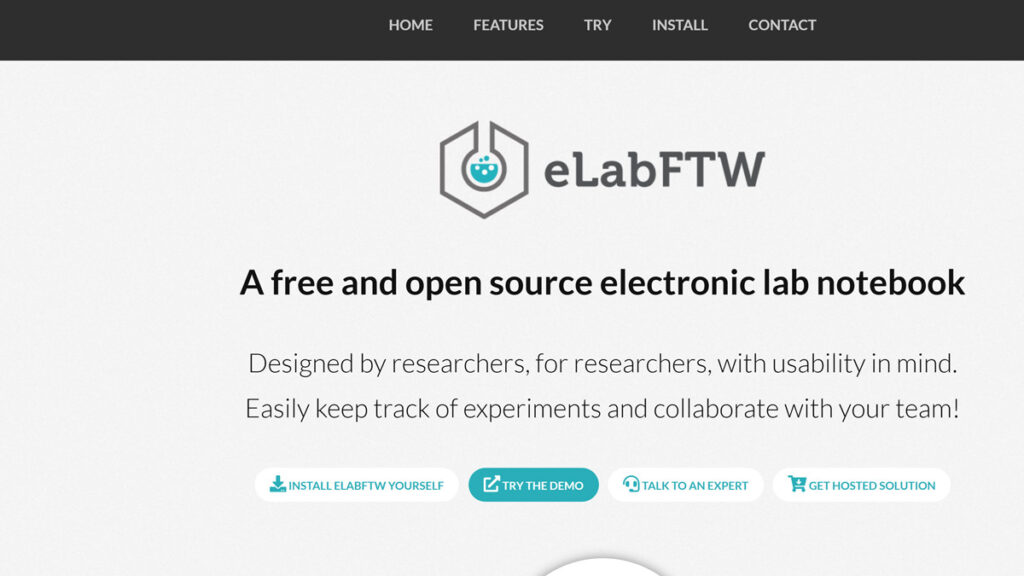
eLabFTWは、無料で利用できるオープンソースの電子実験ノートです。
自社のサーバーにインストールして利用するため、セキュリティポリシーに厳しい組織や、自由にカスタマイズしたい場合に適しています。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 主なターゲット | セキュリティを重視する研究室、ITスキルを持つ研究者 |
| 強み | ・完全オープンソース(AGPLv3)・自社サーバーで運用可能・RFC3161準拠のタイムスタンプ機能 |
| 弱み | ・導入・運用にはサーバー管理知識が必須・公式ベンダーサポートなし |
| 価格帯 | ソフト本体は無料ホスティングサービス:有償(例:年間7,985€〜) |
| 導入実績 | 研究室や機関で自由にカスタマイズして利用可能 |
8. Labfolder:クラウド&タブ型UIで記録しやすいスタンダードELN
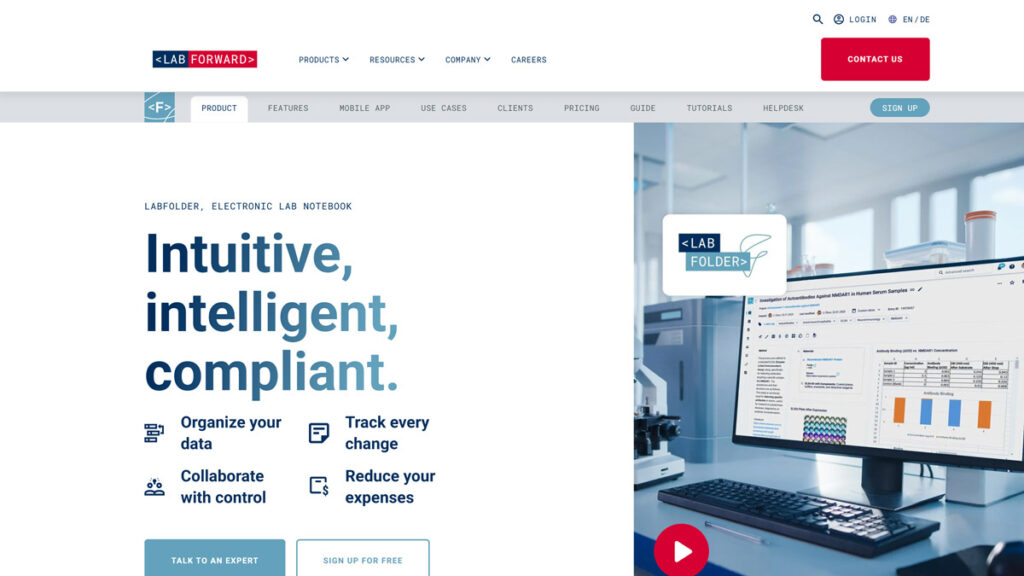
引用元:https://labforward.io/labfolder
Labfolderは、直感的な操作性と堅牢なデータ管理機能を両立させた、バランスの取れたELNです。
タブレット端末での利用にも最適化されており、実験台のそばで手軽に記録を入力したいというニーズに応えます。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 主なターゲット | 学術研究機関、バイオテクノロジー企業 |
| 強み | ・ドラッグ&ドロップの直感的UI ・チームでのコラボレーション機能 ・21 CFR Part 11対応の電子署名 |
| 弱み | ・無料プランは機能制限あり ・高度な分析機能は非搭載 |
| 価格帯 | FreeプランありAcademic:€17/月(年払い) Industry:€52/月(年払い) |
| 導入実績 | 世界中の研究機関・企業で利用実績あり |
機能・目的別で選ぶ!海外電子実験ノート比較一覧表
どのELNが自社に適しているか、一目で比較検討できるように主要な機能を一覧表にまとめました。
研究の目的や重視するポイントに応じて、最適な製品候補を絞り込んでみてください。
| 製品 | 価格・無料プラン | 導入方法 | コラボ機能 | セキュリティ/規制対応 | 日本語対応 |
|---|---|---|---|---|---|
| Benchling | 学術向け無料あり/企業は要問い合わせ | クラウド型 | リアルタイム共同編集 | ISO 27001、SOC 2、21 CFR Part 11対応 | 一部UIのみ |
| IDBS E-WorkBook | 要問い合わせ | クラウド/オンプレ両対応 | 企業向けワークフロー共有 | 21 CFR Part 11、GxP対応 | 一部サポート |
| LabArchives | Freeあり/Academic $330〜/年 | クラウド型 | リアルタイム編集・共有 | ISO 27001、SOC 2、HIPAA、GDPR対応 | 一部UIのみ |
| SciNote | Freeあり/有料は要問い合わせ | クラウド型 | プロジェクト進捗共有 | ISO 27001、Cyber Essentials、21 CFR Part 11対応(有償版) | 英語中心 |
| Labguru | 要問い合わせ | クラウド型 | 実験データ・在庫・機器管理の共有 | 21 CFR Part 11対応 | 一部対応 |
| RSpace | Academic $4,550〜/年〜 | クラウド/オンプレ両対応 | グループ管理・アクセス制御 | 21 CFR Part 11対応 | 英語中心 |
| eLabFTW | 無料(OSS)/ホスティング有償 | オンプレ型(自社サーバー) | 基本的な共有機能 | RFC3161タイムスタンプ機能 | 英語中心 |
| Labfolder | Freeあり/Academic €17〜/月 | クラウド型 | チーム共有・コメント機能 | ISO 27001、21 CFR Part 11対応 | 一部UIのみ |
導入で失敗しない!海外電子実験ノート選定7つのチェックポイント
高価なツールを導入して「結局使われなかった」という事態は避けたいものです。
ここでは、自社に最適なELNを選び、導入を成功させるための7つのチェックポイントを紹介します。
1. 研究分野と組織の規模に合っているか?
まず確認すべきは、ELNが自社の研究内容や組織の規模に適しているかです。
例えば、化学合成がメインの研究室であれば化学構造式エディタが強力な製品、生物学系であれば配列管理や電気泳動画像の注釈機能が充実した製品が望ましいでしょう。
また、数名のチームで使うのか、数百人規模の組織全体で導入するのかによっても、必要な管理機能や拡張性が異なります。
将来的な組織拡大も見据えて、柔軟にスケールできる製品を選ぶことが重要です。
2. 予算と価格体系は適切か?(ライセンス、運用コスト)
ELNのコストは、初期導入費用だけではありません。
年間ライセンス料、ユーザー追加費用、データストレージ費用、保守サポート費用など、長期的な運用コスト(TCO)を考慮する必要があります。
多くの製品で無料トライアルや低価格プランが提供されているため、まずはスモールスタートで試してみて、その価値を実感してから本格導入を検討するのも賢明な方法です。
3. 法的証拠能力とコンプライアンス要件を満たすか?
研究成果を知的財産として保護するためには、ELNに記録されたデータが法的な証拠能力を持つことが極めて重要です。
特に特許申請や規制当局へのデータ提出を視野に入れる場合、以下の機能は必須と言えます。
- タイムスタンプ: いつ、誰が、何を記録したかを証明する機能
- 監査証跡(Audit Trail): 全ての操作履歴を追跡・記録する機能
- コンプライアンス準拠: FDA 21 CFR Part 11やGxPなど、関連する規制要件に対応しているか
4. セキュリティ対策は万全か?
研究データは企業の生命線ともいえる重要な知的財産です。
クラウドベースのELNを選ぶ際は、ベンダーがどのようなセキュリティ対策を講じているかを厳しくチェックする必要があります。
具体的には、データの暗号化、アクセス制御、不正侵入検知システム、そしてISO 27001などの国際的なセキュリティ認証の取得状況などを確認しましょう。
5. 既存システム(LIMS等)と連携できるか?
研究室では、ELN以外にもLIMSや分析機器、データ解析ソフトウェアなど、様々なシステムが稼働しています。
研究データを分断させず、一元的に活用するためには、これらの既存システムとELNがスムーズに連携できるかが重要です。
API(Application Programming Interface)が公開されているか、特定の機器との連携実績があるかなどを事前に確認することで、導入後のデータ活用の幅が大きく広がります。[^3]
6. 研究者が直感的に使えるか?(UI/UX)
どんなに高機能なツールでも、実際に使う現場の研究者が「使いにくい」と感じてしまえば、定着せずに形骸化してしまいます。
導入成功の鍵は、研究者がストレスなく、直感的に操作できるユーザーインターフェース(UI/UX)を備えていることです。
デモや無料トライアルを活用し、実際にデータを入力したり、検索したりする操作を試してみて、日々の業務にスムーズに組み込めるかを確認することが不可欠です。
7. 導入後のサポート体制は充実しているか?
海外製品を導入する際、特に懸念されるのがサポート体制です。
操作方法に迷った時やトラブルが発生した際に、迅速かつ的確なサポートを受けられるかは非常に重要です。
- 日本語での問い合わせに対応しているか
- 日本時間でサポートを受けられるか
- オンラインマニュアルやトレーニング資料は充実しているか
これらの点を確認し、安心して運用を任せられるベンダーを選びましょう。
日本の研究環境にフィットする選択肢「Jikken Note」とは?
海外製ELNは高機能で魅力的ですが、「英語のUIはハードルが高い」「日本の紙文化に慣れているので、完全デジタルは不安」といった声も少なくありません。
そんな日本の研究環境特有の課題に応えるために開発されたのが、私たちの「Jikken Note」です。
海外製品と比較することで、その独自性がより明確になります。
手書きの良さを活かす高精度OCRと紙・デジタルの融合
「Jikken Note」の最大の特徴は、従来の手書きの実験ノートの良さを失うことなく、デジタルの利便性を享受できる点にあります。
使い慣れた紙のノートに記録し、専用のQRコードを使ってスマートフォンでスキャンするだけで、手書きの文字や図を高精度(一般的な手書き文字で認識率 90%)でデジタルテキスト化します。
これにより、検索性や共有性はデジタルで確保しつつ、思考を妨げない手書きの自由さも維持できる、ハイブリッドな運用が可能です。
ワンクリックで実現する国内法規準拠のリスクアセスメント
日本の法令で義務付けられている化学物質のリスクアセスメントは、研究者にとって負担の大きい業務の一つです。
「Jikken Note」は、3,000種類以上の化学物質情報を内蔵しており、実験計画時にワンクリックでリスク評価を完了させることができます。
これにより、コンプライアンスを遵守しながら、研究者の安全確保と業務負担の軽減を同時に実現します。
アズワン株式会社との提携によるシームレスな試薬・機器調達
「Jikken Note」は、国内最大級の理化学機器・試薬サプライヤーであるアズワン株式会社と戦略的提携を結んでいます。
将来的には、「Jikken Note」のプラットフォーム上で実験計画を立て、そのまま必要な試薬や機器をオンラインで発注できるEC機能の統合を目指しています。
これにより、研究計画から物品調達、実験、記録まで、研究ワークフロー全体がシームレスに繋がり、研究活動のさらなる効率化に貢献します。
電子実験ノート「Jikken Note」のサービスとは?>>
電子実験ノート導入に関するよくある質問(FAQ)
最後に、電子実験ノートの導入を検討する際によく寄せられる質問とその回答をまとめました。
自社に最適な電子実験ノートを選び、研究開発を加速させよう|まとめ
この記事では、海外製の主要な電子実験ノート(ELN)を比較し、その特徴や選び方のポイントについて詳しく解説しました。
グローバルな共同研究や厳格なコンプライアンスが求められる現代において、ELNはもはや単なる記録ツールではなく、研究開発の競争力を左右する戦略的基盤です。
海外製品には最先端の機能を持つものが多くありますが、導入を成功させるには、本記事で紹介した7つのチェックポイントを参考に、自社の研究分野、組織規模、そして何より現場の研究者の使いやすさを考慮することが不可欠です。
また、「Jikken Note」のように、日本の研究環境に特化した独自の利点を持つ選択肢も存在します。
ぜひ、この記事を参考に自社に最適な一歩を踏み出し、研究開発を次のステージへと加速させてください。
日本の研究現場に最適な選択肢──Jikken Noteという解決策
海外製の電子実験ノートには優れた機能が数多くありますが、日本語対応や紙文化との親和性に不安を感じた方も多いのではないでしょうか。
そんな国内研究者のニーズに応えるのが、国産ハイブリッドELN「Jikken Note」です。
Jikken Noteが選ばれる理由
- 紙ノートも活かせるハイブリッド構造(手書き→OCR→検索可能)
- リスクアセスメントもワンクリックで実行(法令対応)
- アズワンと連携し、試薬・機器のEC調達まで視野に
- 国内開発・日本語サポート対応で安心
- 化学・生物系に最適化されたテンプレートとUI
実験現場の「使いやすさ」と「証拠力」を両立
Jikken Noteは、従来の手書き文化を尊重しながら、検索性・共有性・セキュリティを飛躍的に高める国産電子実験ノートです。英語UIや複雑な設定が不要で、導入直後から自然に使いこなせる設計が好評。国内の研究環境に即したシステムで、あなたの研究記録を次のレベルへと引き上げます。
今すぐ無料で体験し、研究記録の「手間」を「価値」に変えてみませんか?